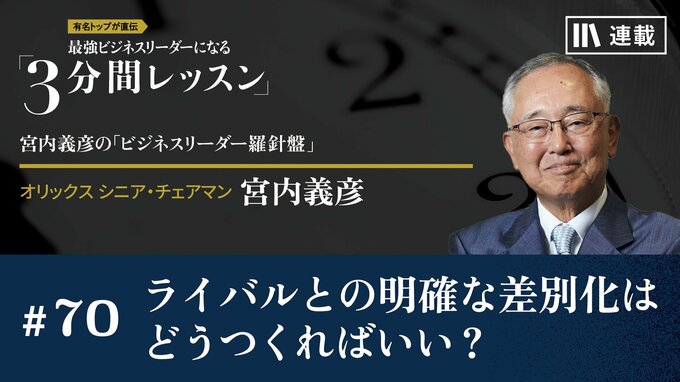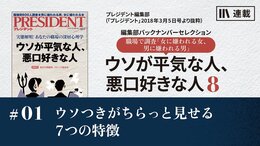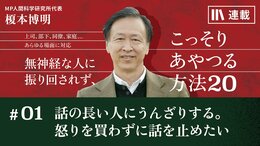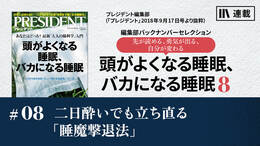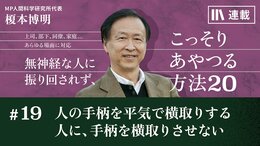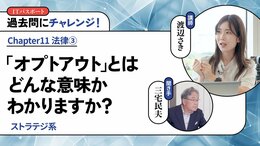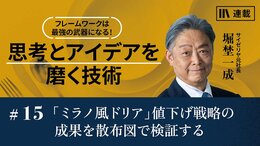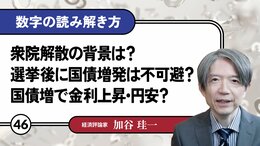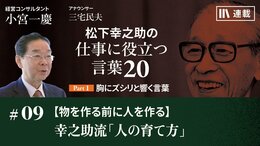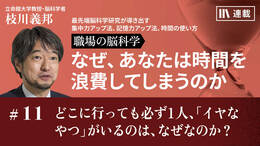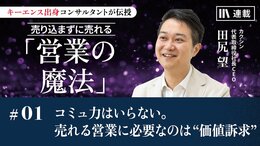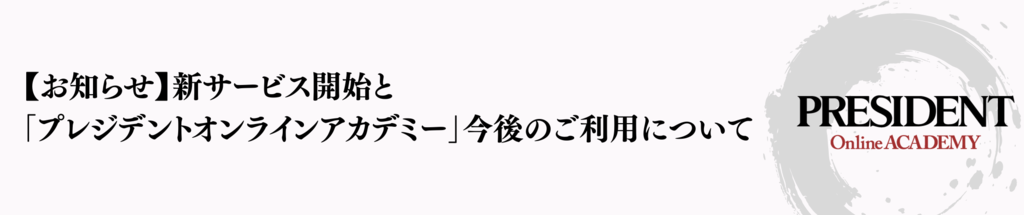オリックス シニア・チェアマンの宮内さんが3分間レッスンの読者のみなさまの質問にお答えします。(2022年2月14日レター)
【読者】情報通信業でコンテンツ事業部長を勤めています。この業界で20年近く働いてきましたが、これまでほとんど差別化のないコンテンツを各社がひしめきあうようにして販売合戦を続けてきました。このままでは進展がないことを頭では理解しているのですが、なかなか変わることができません。
他社がつくれないような強いコンテンツ、強いサービスをわが社でつくりあげたいと考えて取り組んできましたが、新しいものを開発することが非常にむずかしかったです。少し売れると他社が真似して類似商品を出しますし、わが社も他社で話題になっているサービスを真似て類似商品をつくることもありました。この状態が十年一日のごとくに続いてきてしまいました。
このような状況をどうすれば打破できるでしょうか。どうすれば同業他社と商品やサービスの明確な差別化ができるでしょうか。宮内さんのアドバイスをいただければと存じます。
小さなメリット、小さなサービスを付加して勝負することもあり得ます
【宮内】ご質問者は事業部長として悩んでおられるのですが、視点を変えて会社全体から見てみますと、大きな利益にならない事業であっても続けていることに意義があるという場合もあります。
平凡な商品、サービス、この場合では、汎用的なコンテンツであっても、全社的にみてこの部分が必要な商品ラインなのかもしれません。汎用品市場で競っているケースは珍しくもなく、よくある例です。最も典型的な勝ち組は、多額のマーケティング費用、広告宣伝費用を掛けてシェアを大きく伸ばす、売り上げ増をもって何らかの利益を上げる方法です。
水、サプリメント、金融商品などを想像していただくとわかりやすいかもしれません。あるいは、生鮮食品のようなものであれば、他社よりも一日でも早く出荷する、初物として売り出すなど、小さなメリット、小さなサービスで差をつけるというやり方もあり得るでしょう。
必ずしも他社よりも明らかに抜きんでた商品を開発しなければならないと思わずに、ほんの少しほかと違ったサービスに目をつけて、細かな工夫で勝負していくということも、時には意義があるのだと思います。
市場での競争でたとえ勝ち組になっても、それは明日を保証するものではありません。常に新たな創意工夫、あるいは新規投資によって明日の勝ち組になれる備えをしなければならないのです。競争はそういった切ないものであり、果てしのないものなのです。