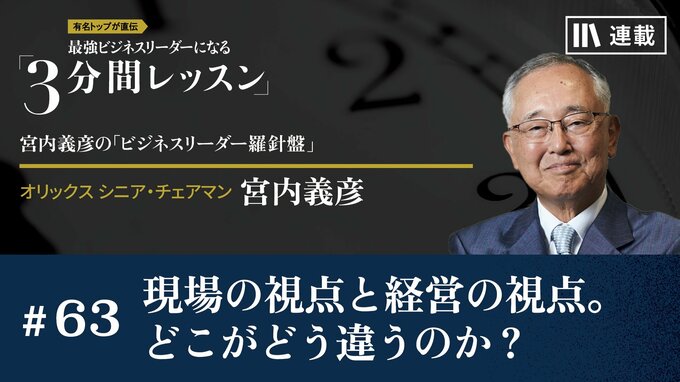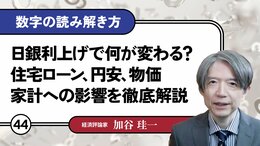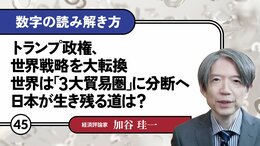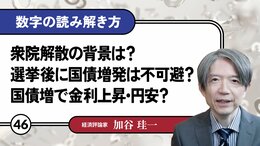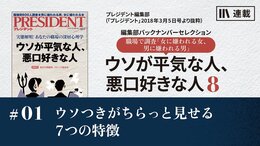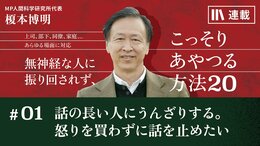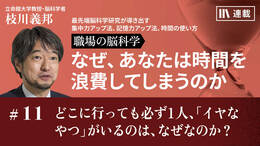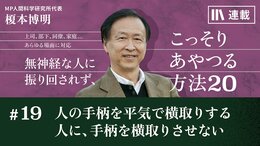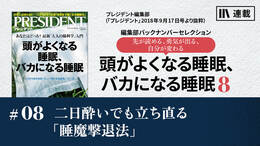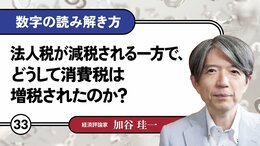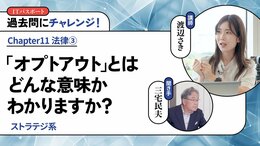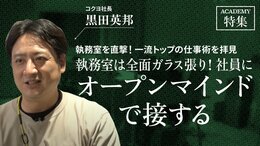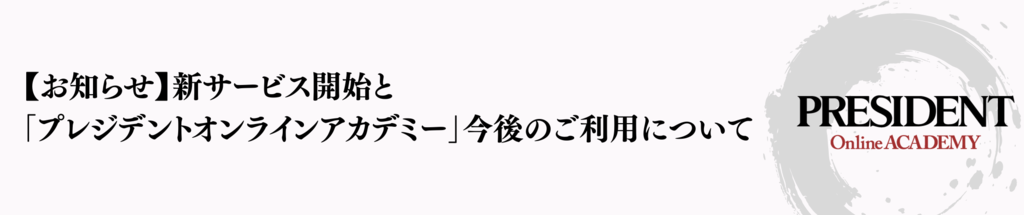オリックス シニア・チェアマンの宮内さんが3分間レッスンの読者のみなさまの質問にお答えします。(2021年12月20日レター)
【読者】中堅の食品メーカーで中間管理職として働いております。30代でこの会社に転職してから10年ほどたちました。
40代になった頃より役員から直接指示を受けるようになり、経営陣の考え方や動き方が分かるようになってきました。経営陣からは販売計画や人事配置など様々な指示が下りてくるのですが、僕の目にはどれも現場のニーズとずれているように映ります。役員には現場の状況を伝えていますので、情報不足ということはないと思いますが、それにしてもチグハグな指示が多いと感じます。経営陣が現場の事情をどれほど理解して判断を下しているのか、不安になります。
その一方で、経営層から見える光景と現場の光景が異なることも理解できます。経営層の大局的な視点からは、僕の方がずれていると映るのかもしれません。中間管理職である僕が経営視点で事業を見ることができるようになるには、どうしたらよいでしょうか? 現場から見るとずれていたとしても、経営判断としては正しいということはあり得るのでしょうか? どうすればそれを理解できるようになるでしょうか? 名経営者と言われる宮内さんに、経営視点と現場視点の違いについて、教えていただければと存じます。
現場視点は現在を、経営視点は将来を見ている、という違いがあります
【宮内】新入社員、中間管理職、経営層で、それぞれ見える景色が違うというのは当然のことと思います。最も大きな違いは情報量とマクロ観ではないでしょうか。マクロ観とは、ものごとを大局的に見る力という意味です。情報量とマクロ観が違えば、その結果として異なる判断を下すことになります。
経営層は、中間管理職層が知らない情報をもっていて、物事を大局的に見て判断していますから、たとえ現場の考えとずれているところがあったとしても、経営層の指示に従うというのが理にかなっていると考えます。
ご質問者が感じていることは、日常的に起こり得ることです。たとえば、現場目線では商品Aがわが社の生命線であり、何が何でもこれをしっかりと作って売っていきたいと考えているとしましょう。その一方で、経営トップの目線では、商品Aは今は売れているかもしれないが、ヒット商品としての寿命はそれほど長くないと見ているので、早く次の商品を開発しなければならない。
そこで、ある日、「一番優れたエンジニアと研究者10人を新規開発部門に異動させる」という指令が製造部門におりてくるわけです。現場ではわけがわからないと受け止めるかもしれませんが、経営陣は次の有望な商品を早急に開発しなければならないと危機感をもって判断したということです。現場としては不安になるのは仕方がないとしても、経営陣はおそらく正しい判断をしているのに違いありません。
現場視点が現在にフォーカスしているとすると、経営視点は広い視野で将来を見ている、あるいは見通さなければならないという違いがあります。ですから、中間管理職層が経営層の視点で物事を見たいと考えるなら、視野を広く持ち、将来の見通しまでを考えられるように努力する必要があります。
有能な経営者は、これから時代はどの方向に向かっていくのか、技術はどのように進歩するのか、それに対してわが社の強みは何であり、どちらの方角にシフトすればよいのか、という視点で物事を考えます。これが、私がつねづねお伝えしているマクロ観にほかなりません。
先の例で、もし私が中間管理職であれば、経営者の考えていることをできるだけ理解する努力をするとともに、現場の混乱を避けるのも重要なので、人事異動のインパクトを和らげるよう、人数、時期などを経営層とすり合わせをさせてもらう機会を作ろうと考えると思います。