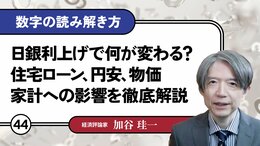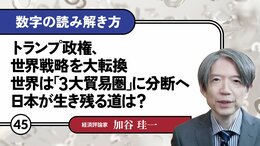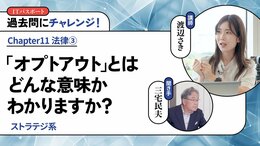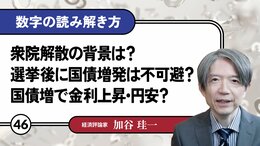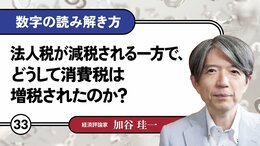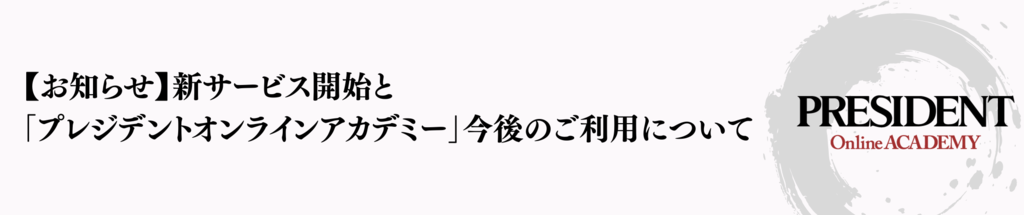プロ野球界きっての名将であり、人材育成の達人でもあった野村克也さん。生前の彼が遺した膨大な箴言、名言の数々は、没後3年が経過してもなお、現代を生きるわたしたちにとっての示唆に富んでいます。部下を一人前にするために、上司がするべきこととは何か? 生前の野村さんへの、そして現在でも野村さんの周囲にいた人々への取材を精力的に続けているノンフィクション作家の長谷川晶一さんが解説していきます。
「答えは自分で探すもの」という信念
人材育成において、野村克也は「教えるな。質問を投げかけよ」と説いている。あるいは、メジャーリーグの格言である「教えないコーチが名コーチ」をしばしば引用したり、「教えるではなく、見つける」と口にしたりもしている。ヤクルト監督時代には、「指導者とは、気づかせ屋」との信念の下、池山隆寛や広沢克己(廣澤克実)ら、円熟期に差しかかりつつあった中心選手の指導を行っている。
これらの発言の根底にあるのは、「答えは自分で探すもの」という野村の思いである。言い換えるならば、「他人から与えられた答えは身につかない」という考えであり、現役時代に体得した自らの体験に基づいている。
野村がまだ若かった昭和30~40年代のプロ野球界では、現在と比較してコーチの数は圧倒的に少なかった。したがって、野村に限らず当時の選手たちは自ら創意工夫を繰り返しながら技術を磨いていた。「これぞ!」と思った選手のフォームを食い入るように見つめ、すぐに真似をして自分のものにしようと試みた。
当時、プロ野球の世界では、技術は「教わるものではなく、見て盗むもの」という考えが一般的だった。先輩たちが試行錯誤の果てに体得した技術に対して、安易に「教えてください」などと口にできるはずもなく、当の先輩たちもまた「商売敵にメシの種を教えられるはずがない」という考えが一般的だったのだ。
しかし、時代は変わった。先輩と後輩との距離は縮まり、コーチの数も圧倒的に増え、かつてのようなギスギスした上下関係は遠い時代の出来事となった。「教える者と教わる者」の対等な関係もあたりまえのこととなった。それでも野村はなおも、指導者の心得として「教えるな。質問を投げかけよ」と説くのである。それは一体、どうしてなのだろう?
ヤクルト・髙津臣吾監督に息づく「野村の教え」
東京ヤクルトスワローズを率いる髙津臣吾監督にインタビューしたときのことである。2020年2月――、野村が亡くなってすぐのことだった。恩師との思い出を尋ねた後、「野村さんから教わったことは?」と質問を投げかけると、髙津監督はこんなことを口にした。
「野村監督は常々、『監督とは気づかせ屋だ』とおっしゃっていました。現在、自分も監督という立場になって思うのは、選手に対して答えを提示してあげることは、意外と簡単だということ。でも、それだと本当の実力は身につかないと痛感しています。課題を克服して技術を自分のものとするためには、与えられた答えではなく、何度も挑戦して自分で見つけた答えでなければダメなんです」
まさに、「野村イズム」が浸透していることをうかがわせる発言である。どうして、彼がこんな思いを抱くようになったのか? きっかけは高津の現役時代の1993年、ペナントレースがはじまる前のことだった。野村は彼を呼び出し、「150キロの腕の振りで遅いスライダーを投げられるか?」と問うたという。
「前年の日本シリーズでヤクルト打線は、西武・潮崎哲也のシンカーに完全に抑え込まれました。それを見て野村さんは『速い球でなくても抑えられるんだ』ということを僕に伝えたかったんでしょう。だけど、出題するほうは簡単ですけど、実際に答えを見つけるのは本当に大変でしたよ(笑)」
「答え」ではなく、「問い」を投げかける意味
ここから髙津の試行錯誤の日々がはじまる。もともと彼が投げていたシンカーは120~125キロ程度だった。しかし、野村は「100キロくらいで投げろ」といい、同時に「150キロの腕の振りで」とつけ加えたのである。
「何度も『こんなことできないよ……』と思いながら、いろいろと握りを変え、様々な腕の振りで試行錯誤を繰り返し、ようやく1993年の夏頃から、相手打者のタイミングがずれはじめたのがわかりました。この年の日本シリーズで僕が胴上げ投手になることができたのは、間違いなく100キロ台のシンカーのおかげでした」
その後、リーグを代表するクローザーとなった髙津は、1997年には110キロ台のシンカーもマスターする。その結果、120キロ台の速いシンカー、100キロ台の遅いシンカー、そしてその中間である110キロ台のシンカーと3種類を投げ分けられるようになり、この年も日本一となった。それは、野村監督の「問い」に対する「答え」を探し求めた結果でもあった。
「いまから思えば、野村監督の言葉はいつも《答え》ではなく、《問い》でした。選手に問題を投げかけることで、自分たちで答えを探すように仕向けていました。必死に答えを探したからこそ、僕の野球人生は幸せなものとなりました。もちろん、誰に対しても同じやり方が通用するとは限らないけれど、自分も監督となった以上は選手たちにいい気づきを与えられるような《問い》を投げかけるつもりです」
相手に「責任感」を持たせ、「依頼心」をなくす
野村は、自著『野村克也全語録 語り継がれる人生哲学』(弊社刊)において、こんな言葉を遺している。
「わたしは毎日のようにミーティングを行っていたが、ひとつだけ心掛けていたことがあった。それは、『答えまでいわない』ということである。答えは、必ず選手にいわせる」
それは一体、どうしてなのか? 野村が重視したのは「責任感」であり、「考える力」だった。再び、前掲書から引用したい。
「質問に対して選手が答えを出せば、それは答えをいった選手の『責任』になる。自分でいったことには誰しも責任感を持って取り組むもので、それがいつしか、選手個々の使命感になっていく。だから、『答え』は選手にいわせるべきだとわたしは思うのだ」
そして、指導者が手取り足取り指導することで、選手に依頼心が芽生え、その結果、選手の持つ「考える力」が奪われかねないと指摘する。
「依頼心が強くなるほど、人間の思考力は衰える。思考が止まれば、進歩も止まる」
先に挙げた髙津臣吾のシンカー習得の例を思い出してほしい。野村が口にしたのは「150キロの腕の振りで遅いスライダーを投げられるか?」という「問い」だった。決して、「投げろ」という命令形ではなかった。監督からの要望には強い影響力があり、実質的には「命令」に近いものかもしれない。けれども、野村はあくまでも「問いかけ」にこだわった。
こうして髙津は、「責任感」を持って遅いスライダーの習得に励み、実際にそれをモノにしたことで球界を代表するクローザーに成長した。そこには、「依頼心」は微塵もなかった。自分自身でやるしかなかったからだ。まさに、野村の狙い通りの成果をもたらすことになった。だからこそ、野村は言うのだ。
「教えるな。質問を投げかけよ」、と。
部下を一人前に育て上げるには、「本人の依頼心を排除する」という上司の姿勢が重要になる。そのためにすべきことは「答え」を提示することではない。「問い」を投げかけることなのである。