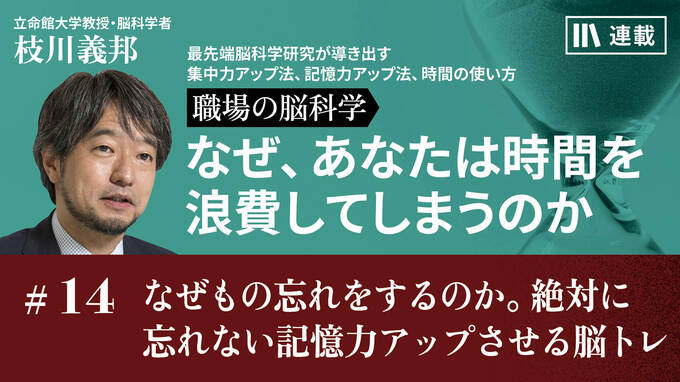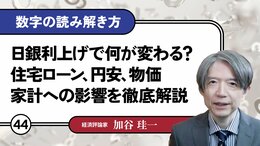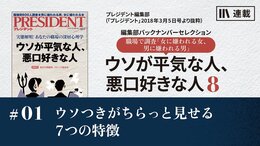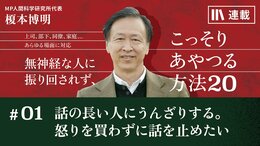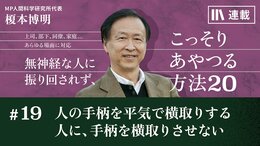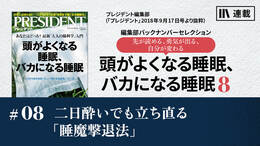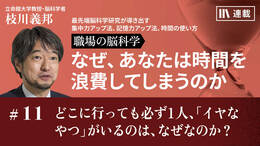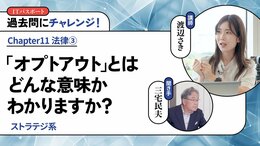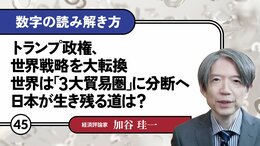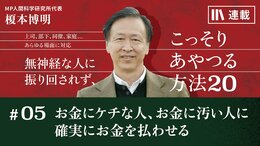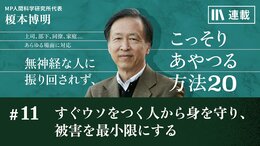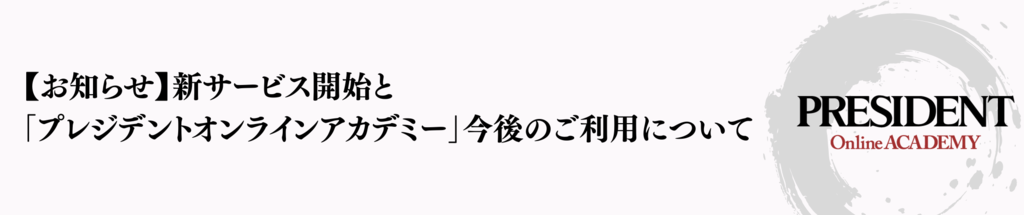もの忘れについて考えるにあたり、まず、「人はなぜ記憶するのか」について考えてみましょう。記憶の構造を理解することで、能力向上の方法も見えてきます。食事、栄養摂取、生活スタイルから記憶術など、さまざまな観点から記憶力をアップさせる方法を紹介します。
思考や創造性などの中枢を担う「作業記憶」
「あの人の名前は何て言ったかな? 顔は思い出せるんだけれども、名前をどうしても思い出せないぞ!」
ご無沙汰してしまっていた取引先に連絡を入れようとしたのに、相手の名前がなかなか浮かんでこない。何度も会ったことのある相手だけに、頭の中の片隅に記憶として残っているのは確かで、あとちょっとで出てきそうな気がする。若い頃だったら、すぐに思い出せたはずなのに……。40代、50代になると、このような「ど忘れ」がたび重なって起きるようです。
そもそも人は、なぜ記憶するのでしょう。それは、いまその人が置かれた環境下で、最適な立ち居振る舞いができるようにするためです。例えば、アフリカの大草原にいてライオンを見かけたとき、「自分にとって危険な獣である」という記憶がなく、そのまま通り過ぎようとしたら、食べられてしまうかもしれません。
私たちは、「視覚」「聴覚」「嗅覚」「味覚」「触覚」という「五感」を通して、外界から様々な情報を受け取っています。その情報は、脳で処理できる形となった後、前頭前野を中心とした「ワーキングメモリ」のテーブルに載せられたり、「大脳辺縁系」と呼ばれる大脳の奥にある「海馬」へ送られます。そして、その海馬で記憶に関連した神経ネットワークを活発に働かせることによって、必要とされる情報が「長期記憶」として「大脳皮質」に刻み込まれ、定着していきます。
そうした記憶の情報は、「記銘」「保持」「想起」という3つのステップを経ることが知られています。まずは、外界から脳へ入ってきた様々な情報を脳が獲得して、記憶情報とする「記銘」のステップです。次に、記憶した情報を蓄えておく「保持」のステップに移ります。そして最後に、それら記憶として蓄えていた情報を思い起こす「想起」のステップへ続いていきます。